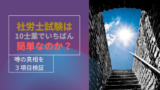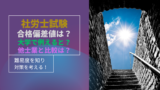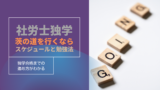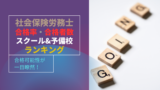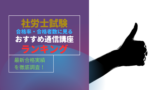社会保険労務士試験の難易度を客観的に知りたい。
難易度ランキング比較では?宅建や行政書士と比較すると?偏差値を大学で例えると?
この記事では社労士試験の難易度についてさまざまな角度から比較と検証をしました。
❶ 社労士の10士業における難易度比較ランキング
・合格率の比較ランキング
・必要な勉強時間の比較ランキング
・平均的な年収の比較ランキング
・社労士の難易度総合比較ランキング
❷ 宅建士との難易度比較
・合格率の比較
・勉強時間の比較
・年収の比較
❸ 難易度を偏差値で考えると?
・2023年の社労士合格偏差値は65
・大学群で比較した場合の目安
・実際の社労士受験は実力勝負
❹ 週刊ダイヤモンド衝撃記事の真相は?
・衝撃的なコメントとは
・真相の検証結果は?
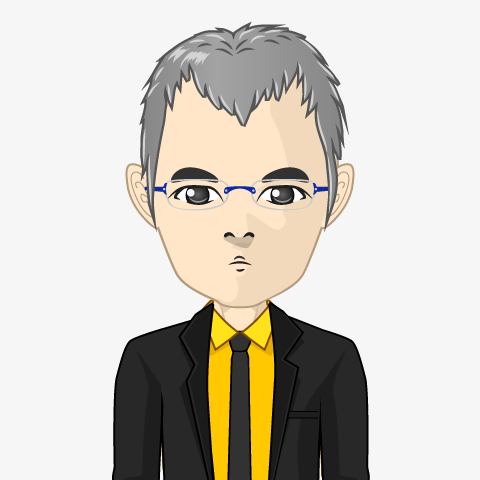
◉ 入社後人事部門配属を期に人生挽回のため社労士受験を決意
◉ 地方在住で予備校もお金もなく独学メインに勉強
◉ 複数ツールを組合せたハイブリッド勉強法で社労士合格
満足いかない就職活動と地方配属というアウェイな状況から、ネガティブな不満を燃料にして試行錯誤しながら行き着いた、社会人が独学メインで社労士合格するための効果的手法やお役立ち情報を発信しています。
❶ 社労士の10士業における難易度比較ランキング
社労士試験の難易度を客観的に検証するためにまずは他の士業の資格試験と比較してみました。社労士の難易度について、行政書士や中小企業診断士と比較されることが多いので、それらを含む代表的な士業として10士業における難易度をランキング形式で比較しました。
10士業とは、社会保険労務士、土地家屋調査士、中小企業診断士、行政書士、弁理士、公認会計士、不動産鑑定士、弁護士、司法書士、税理士 になります。
※この順番は、東京都社会保険労務士会ウェブサイト記事に倣いました。

難易度が客観的に測ることができる3項目として、①合格率、②勉強時間、③年収を挙げました。合格率と勉強時間は資格試験の難しさそのものですが、年収は、士業の付加価値が高い難しい仕事の対価として受け取る報酬と考えられますので比較項目として入れています。
①合格率、②標準勉強時間、③平均年収 → 総合比較ランキング
比較の方法は、それぞれの比較項目について1位~10位までそれぞれ10点~1点のポイントとして単純に合計金額で比較してみたいと思います。
合格率の10士業比較ランキング
※参考サイト 各実施団体等ウェブページ(2020年)
| 1. | 司法書士 | 4.1% | 10点 |
| 2. | 弁護士(司法試験予備試験) | 4.2% | 9点 |
| 3. | 社会保険労務士 | 6.4% | 8点 |
| 4. | 弁理士 | 9.7% | 7点 |
| 5. | 公認会計士 | 10.1% | 6点 |
| 6. | 土地家屋調査士 | 10.4% | 5点 |
| 7. | 行政書士 | 10.7% | 4点 |
| 8. | 中小企業診断士 | 18.4% | 3点 |
| 9. | 税理士 | 20.3% | 2点 |
| 10. | 不動産鑑定士 | 33.1% | 1点 |
やはり司法試験予備試験と司法書士の合格率は低いですね。とはいえ、社労士は⒍4%で堂々の3位です。もちろん各士業の試験制度や年度による変化があることが前提ですが。
よく比較される、行政書士や中小企業診断士と比べると社労士の合格率は低いことがわかります。中小企業診断士は合格した科目は翌年の試験では免除される制度があり計画的に科目合格を目指す方法がありますが、社労士試験では合格基準を超えた科目でも全体として不合格になれば翌年の試験で免除されることはありませんので、試験としての難易度が上がり合格率が下がることになります。
必要な勉強時間の比較ランキング
※参考サイト アガルートアカデミー| 1. | 弁護士(司法試験予備試験) | 6000時間 | 10点 |
| 2. | 公認会計士 | 3500時間 | 9点 |
| 3. | 司法書士 | 3000時間 | 8点 |
| 3. | 弁理士 | 3000時間 | 8点 |
| 5. | 税理士 | 2500時間 | 6点 |
| 6. | 不動産鑑定士 | 2000時間 | 5点 |
| 7. | 社会保険労務士 | 1000時間 | 4点 |
| 7. | 土地家屋調査士 | 1000時間 | 4点 |
| 7. | 中小企業診断士 | 1000時間 | 4点 |
| 10. | 行政書士 | 600時間 | 1点 |
勉強時間時間で比較しますと社労士は土地家屋調査士、中小企業診断士と並んで1000時間で7位タイという結果で、それよりも少ないのが行政書士のみということになります。もちろん、こちらも分野の知識の土台の有無や勉強効率にもよりますが。
平均的な年収の比較ランキング
※参考サイト 給料BANK、中小企業診断士のみ中小企業診断協会調査結果参考のコンサル白書
| 1. | 弁護士(司法試験予備試験) | 1168万円 | 10点 |
| 2. | 公認会計士 | 880万円 | 9点 |
| 2. | 税理士 | 880万円 | 9点 |
| 4. | 司法書士 | 864万円 | 7点 |
| 5. | 中小企業診断士 | 780万円 | 6点 |
| 6. | 不動産鑑定士 | 752万円 | 5点 |
| 7. | 社会保険労務士 | 640万円 | 4点 |
| 7. | 弁理士 | 640万円 | 4点 |
| 9. | 土地家屋調査士 | 574万円 | 2点 |
| 10. | 行政書士 | 531万円 | 1点 |
収入は提供する付加価値と相関があるので、士業でビジネスをしている方の平均年収を調べてみました。調査対象の幅が大きくて平均値で比較することには限界がありますが、合格に必要とされる勉強時間が最も多い司法試験予備試験を経た弁護士の年収が最も多いことは興味深いですね。
単純には判断出来ませんが、努力は報われることがある意味で実証されています。社労士は奇しくも勉強時間と同じく7位タイです。5位の中小企業診断士より若干少ないものの10位の行政書士を上回る結果となっています。
社労士の難易度総合比較ランキング
それでは社会保険労務士の難易度について、十士業における①合格率、②勉強時間、③年収の比較ランキングを総合した結果を検証してみましょう。
| 1. | 弁護士(司法試験予備試験) | 29点 | |
| 2. | 司法書士 | 25点 | |
| 3. | 公認会計士 | 24点 | |
| 4. | 弁理士 | 19点 | |
| 5. | 税理士 | 17点 | |
| 6. | 社会保険労務士 | 16点 | |
| 7. | 中小企業診断士 | 13点 | |
| 8. | 不動産鑑定士 | 11点 | |
| 8. | 土地家屋調査士 | 11点 | |
| 10. | 行政書士 | 6点 |
総合順位で社労士は6位という結果になりました。並み居る十士業の中でほぼ真ん中の難易度ということができそうです。
社労士の難易度は10士業難易度ランキング6位
よく比較される、中小企業診断士、行政書士との比較では、中小企業診断士 7位、行政書士 10位に比べ社労士試験の難易度が高いという結果になります。
❷ 宅建士との難易度比較
十士業には含まれませんが、社労士試験の難易度を比較する際に宅建士(宅地建物取引士)と比べられることが多いようです。ここでは、10士業難易度ランキングと同様に、難易度が客観的に測ることができる3項目として、①合格率、②勉強時間、③年収について社労士VS宅建士を比較します。
①合格率、②標準勉強時間、③平均年収 → 社労士VS宅建 難易度比較
比較の方法は、それぞれの比較項目について単純に勝敗で比較してみたいと思います。
宅建との合格率の比較
データが揃う2021年(令和3年)の試験結果で比較します。
| 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | |
| 社会保険労務士 | 7.9% | 37,306名 | 2,937名 |
| 宅建士 | 17.7% | 234,714名 | 41,471名 |
合格率の比較では社労士 7.9%に対して宅建は17.7%と大きな差が出ています。倍率の観点で見ると、社労士が約13人に1人の合格に対して、宅建は約6人に1人の合格となっており、社労士の合格率が低く難易度が高いことがわかります。受験者数、合格者数の規模は異なっていて業界における位置付けの違いも感じられます。
宅建との必要な勉強時間の比較
宅建の合格圏までの平均的な勉強時間の目安は300時間から400時間程度です。これはあらかじめ法律知識がない所学者の場合で、他の資格を取得していて民法などの知識が既にある場合にはもう少し短くなるようです。
| 社会保険労務士 | 800〜1,000時間 |
| 宅建士 | 300〜 400時間 |
一方で社会保険労務士は合格圏までの平均的な勉強時間の目安は800〜1,000時間というのが通説です。社労士は宅建士の2倍以上の勉強時間を要することから、勉強時間の面で社労士試験の方が難易度が高いということができます。
宅建との平均的な年収の比較
※参考サイト 給料BANK
| 社会保険労務士 | 640万円 |
| 宅建士 | 480万円 |
年収については十士業の比較と同様に提供するサービスの難易度が付加価値の高さとして報酬として得られると考えます。これを見ても社労士が大きくリードしていることがわかります。
では総合的に判断してみましょう。
①合格率 社労士
②標準勉強時間 社労士
③平均年収 社労士
全項目で社労士の方が難易度が高いということが検証されました。
❸ 社労士の難易度を偏差値で考えると?
難易度を客観的に示す指標として偏差値があります。偏差値とは、言わずと知れた平均を真ん中として上か下にどのぐらい離れているかで優劣を図る指標です。
2023(令和5)年の社労士合格偏差値は65
受験者の半分が合格する資格試験なら偏差値50ということになりますが、社労士試験の合格率6.4%(2023年:令和5年)です。下記の早見表から上位6.4パーセントはどの偏差値に該当するでしょうか?
【偏差値の早見表】
| 偏差値 | 上位パーセント | 何分の1か |
| 70 | 2.3% | 44 |
| 69 | 2.9% | 35 |
| 68 | 3.6% | 28 |
| 67 | 4.5% | 22 |
| 66 | 5.5% | 18 |
| 65 | 6.7% | 15 |
| 64 | 8.1% | 12 |
| 63 | 9.7% | 10 |
| 62 | 11.5% | 9 |
| 61 | 13.6% | 7 |
| 60 | 15.9% | 6 |
| 59 | 18.4% | 5 |
| 58 | 21.2% | 5 |
| 57 | 24.2% | 4 |
| 56 | 27.4% | 4 |
| 55 | 30.9% | 3.2 |
| 54 | 34.5% | 2.9 |
| 53 | 38.2% | 2.6 |
| 52 | 42.1% | 2.4 |
| 51 | 46% | 2.2 |
| 50 | 50% | 2.0 |
合格率6.4%はこの表の赤文字の偏差値65の少し上あたりです。つまり受験者の中で偏差値65以上に入らないと合格圏に入れないことになります。社労士試験の難易度が客観的に見て高いことがわかります。
ちなみに社労士試験の過去10年間の合格率の推移はこちらです。昨年まで5年間の合格率は6〜8パーセント、偏差値64〜65と比較的安定しています。令和4年の合格率は5.3%、偏差値66と難化しましたが、令和5年の合格率は6.4%、偏差値65と戻しました。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2023年度(令和5年) | 42,741 | 2,720 | 6.4% |
| 2022年度(令和4年) | 40,633 | 2,134 | 5.3% |
| 2021年度(令和3年) | 37,306 | 2,937 | 7.9% |
| 2020年度(令和2年) | 34,845 | 2,237 | 6.4% |
| 2019年度(令和元年) | 38,428 | 2,525 | 6.6% |
| 2018年度(平成30年) | 38,427 | 2,413 | 6.3% |
| 2017年度(平成29年) | 38,685 | 2,613 | 6.8% |
| 2016年度(平成28年) | 39,972 | 1,770 | 4.4% |
| 2015年度(平成27年) | 40,712 | 1,051 | 2.6% |
| 2014年度(平成26年) | 44,546 | 4,156 | 9.3% |
社労士試験の合格率が最も低かった2015年の合格率は2.6%でしたので、同じようにこの表に当てはめると、偏差値69以上ということになります。この年の難易度は特別ですが、社労士を目指すにあたり難易度を認識しておく必要があります。
大学群で比較した場合の目安
数字だけではイメージが湧かないという方に、大学で言うとどのランキングになるか比較してみたいと思います。もちろん、受験者層も違えば受験科目も違いますので比較ランキングにすること自体に無理があると言う前提ですが。
◉ 偏差値64〜66あたりの大学(法学部)
※入試難易予想ランキング表より(2024年5月現在)
河合塾ランキング表では2.5刻みのため偏差値65の大学を表示します。
62.5-65 上智大学 法学部、 中央大学 法学部、 同志社大学 法学部
法律関連の資格ということで法学部を選びましたがトップクラスの難関大学ばかりですね。
実際の社労士受験は実力勝負
ここまでの検証から社労士の難易度が高いことを認識して試験勉強に取り組む必要がありますが、社労士試験合格には卒業した大学はまったく関係がありません。高校卒であっても実務経験などクリアすれば同じ土俵で競い試験当日に基準以上の点数が取れれば合格です。
❹ 週刊ダイヤモンド衝撃記事の真相は?
番外編ですが、社労士の難易度比較という面で衝撃的なコメントが週刊ダイヤモンドの記事に掲載されたのをご存知でしょうか?
衝撃的なコメントとは
「十士業」の中で、社労士試験は「最も簡単」!?
週刊ダイヤモンド7月24日号の記事にベテラン社労士のコメントとして、こんなコメントが掲載されました。

「特集 弁護士・司法書士・社労士 序列激変」と題した記事特集で、新たなニーズから今後社労士の出番が増えて社労士の地位が向上するという趣旨から、話の流れから現在の社労士の地位をあえて低く定義する必要があったとは言え、聞き捨てならないコメントですね。
真相の検証結果は?
独学メインで社労士試験に向けて休日や睡眠時間を削って身も心も削って2回目のチャレンジで何とか合格した私としてはやすやすと聞き流す訳にはいきません。ということで、
①合格率、②標準勉強時間、③平均年収 の3項目について
独自の観点で本当に社労士は十士業で一番簡単なのかを検証してみました。
結論としては「十士業」の中で、社労士試験は「最も簡単」は言い過ぎ
という結果に。真相の検証結果はこちらの記事を参照ください。
【話題の記事の真相を独自に検証】
社労士試験の難易度を客観的に検証するために、比較ランキングによる行政書士、中小企業診断士との比較をしたり、難易度を偏差値で表して大学入試難易度と比較しました。独学でもスクールでも社労士の難易度を把握したうえで自分に合った準備をしていくことが合格への近道といえます。
❶ 社労士の10士業における難易度比較ランキング
・合格率の比較ランキング
・必要な勉強時間の比較ランキング
・平均的な年収の比較ランキング
・社労士の難易度総合比較ランキング
❷ 宅建士との難易度比較
・合格率の比較
・勉強時間の比較
・年収の比較
❸ 難易度を偏差値で考えると?
・2022年の社労士合格偏差値は66
・大学群で比較した場合の目安
・実際の社労士受験は実力勝負
❹ 週刊ダイヤモンド衝撃記事の真相は?
・衝撃的なコメントとは
・真相の検証結果は?
気になる! 社労士の偏差値は?大学で例えると?
2023年の社労士合格率6.4%、偏差値に換算すると65、過去10年間の偏差値推移は?大学ランクならどこ?旧帝?早慶?司法書士や行政書士など士業や難関資格20資格で偏差値比較も。
【社労士を独学で目指す方に】
【宅建士を独学で目指す方に】
合格の近道は実績あるスクール・講座を選ぶこと
社労士のスクール・講座の実力が一目瞭然!合格率・合格者数ランキング
◉ 社労士通信講座を探している方に!
一概におすすめと言っても、勉強スタイルや好みで選ぶべき講座が変わってきます。
よく講座比較サイトではランキング評価でおすすめを決めていますが、いくらよい講座でも自分のスタイルに合わない講座を選ぶと失敗します。こちらで自分だけに合う社労士講座が見つかります。
注目! 絶対的おすすめの社労士講座とは
本当におすすめの社労士講座とは社労士試験に合格できる講座です。つまり合格率が高く合格者数が多い予備校や通信講座。
とはいえ社労士講座は戦国時代!順位が毎年変動します。そこで最新2023年の予備校・講座の合格率・合格者数をランキング一覧。